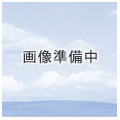- 検討スレ
- 住民スレ
- 物件概要
- 地図
- 価格スレ
- 価格表販売
- 見学記
北海道で3月に地元の工務店で建てました。
しかし朝起きると、サッシやその周りの壁が結露して困っています。
設計時から結露しない家を望んでいたので、正直ガッカリです。
小さい子供がいるので夜間のみ加湿器を最弱で使用しています。
温室度計で真夜中に測ると、19度の55パーセントでした。
加湿器の使い過ぎで結露しているのでしょうか?それとも設計、施工の問題でしょうか?
結露で壁紙も濡れている状態なので、カビも心配です。(朝起きたらこまめに拭き取るようにはしていますが・・)
何か良い対策はないものでしょうか?
下記が家のスペックです
サッシ:YKKプラマードⅢ
第一種換気(弱で24時間連続運転)
断熱:軸間GW200ミリ+付加断熱ネオマフォーム30ミリ
窓下に温水パネルヒーター設置し、夜間も運転
全窓にハニカムサーモスクリーン設置
C値:1.1?(確認中です)
Q値:1.3
工務店に尋ねると、「一種換気とハニカムサーモスクリーンの組み合わせならある程度の結露は仕方がない」との返答でした。
何か良い対策はないものでしょうか?
アドバイスをお願い致します。
[スレ作成日時]2011-03-28 12:50:38